突然ですが一般科の皆様、センスのない精神科務めの皆様。
症状だけを見て病名を判断していませんか?もしくは薬だけを見て病名を判断していませんか?
精神疾患の診断はかなりの専門的知識と経験を有する。「医師が変われば疾患名は変わる」なんてこともよくある話だ。疾患名が変われば薬も治療方針も変わる。
症状だけをみて疾患名の判断などすべきではない、下手すれば患者が死ぬ。
統合失調症患者には、しばしば「うつ(※ここでは気分障害のうつ)」のような症状が見られる。具体的には活気が見られず、食事も取れない、表情も乏しい等である。
しかし、そこだけをみて抗うつ薬(パキシル等)で使用しようものなら統合失調症の行動障害を惹起されることが想像つくだろう?統合失調症患者の死因として自殺率が高いのは事実である。双極性障害についても鑑別診断すべきであろう。
精神科医の診断はそれだけ重要なものである。
「統合失調症」「双極性障害」「認知症」この診断をみて(患者本人・患者家族から聞いて)あなはどう捉えどう向き合う?処方された薬の意味は?
本記事では疾患名の捉えかたについて、これから精神科を学ぶ皆様に向けて記事を書こうと思う。
ICD-11とDSM-5
精神疾患を理解するうえでDSM-5 と ICD-11は重要である。その違いをざっくり説明すると 、DSM はアメリカ精神医学会の出した精神障害のみの診断分類に対してICD -11は世界水準で公表されているこの世のほぼすべての疾病の診断分類。精神科領域は「F」である。
どちらが優れているというのではなく、どちらも参考にして疾患への理解を深めます。
おすすめはICD-11の「F」でイメージを掴み、DSMで学ぶと良い
F0症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
ざっくりICDのイメージ
F0:器質異常
F1:薬物依存
F2:統合失調症
F3:うつ、双極性障害
F4:心身症
以上
特に重要なF0とF2
あくまで個人的な意見として精神疾を理解するうえでF0とF2が重要であると考える。
すなわち「心に問題があるか(F2)」「脳に問題があるか(F0)」。
- 脳に問題がある(F0)
アルツハイマー型認知症」、「てんかん性精神病」など器質的異常、脳波ノイズに伴う精神疾患である。脳梗塞後の精神疾患も場合によってはここに分類される。病名に固執していただきたいのでここで上げる疾患名は参考程度にしてほしい。
- 心に問題がある(F2)は「統合失調症」である。説明はいらないだろう。
一般的に勘違いされるが統合失調症は陽性症状と陰性症状だけではない。「陽性症状」「陰性症状」「攻撃性」「抑うつ」「認知機能低下」の5つが精神症状である。
F0とF2の関係性
ベンゾジアゼピン編でもすこし触れたがもう少し詳しく触れておこう。
精神疾患を理解する際、精神病(F2)とてんかん(F0)を正反対のスペクトラムだとイメージすると良い。他の疾患は上記に加えパーソナル(人格)とムード(気分)の複合型と意識すれば良い。
それらについては後日、記事にする。
- F2の治療(メジャートランキライザー)はてんかんを起こす。
電気けいれん療法(無理やりてんかん発作を起こす医療)があるぐらいだ。
- てんかん(F0)の治療(抗てんかん薬、マイナートランキライザー)はせん妄を起こす。
最後に
疾患名に対し少し理解が深まっただろうか?今回はゼロぐらいから精神科医療に参入される方にむけて記事を書いた。一番大事なのは眼の前の患者に対し精一杯務めることである。しかし、無知は罪である。閉鎖されてきた疾患領域に全力で向き合ってほしい。

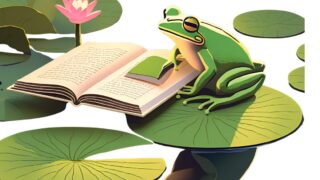



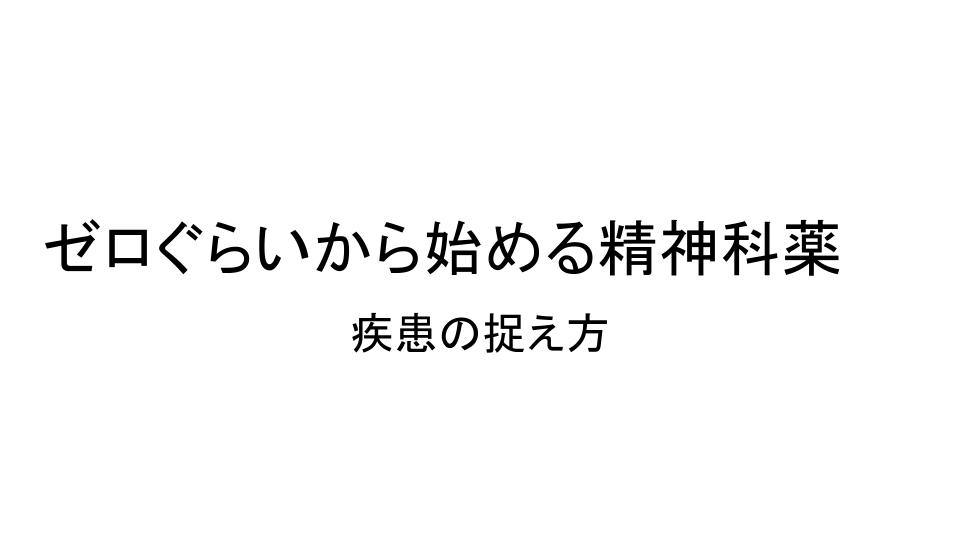


コメント