抗精神薬(メジャートランキナイザー)について記事にしようと思ったが内容があまりに重厚である。個人的にはメジャーは精神科薬の中核であると感じておりしっかりと記事にしたい。一般科から精神科へ転職した10年前の自分に見てほしいとも思えるぐらいの記事にしたいと考えている。そこで今回はアイスブレイクとして精神科に興味を持ってもらうため、メジャー編を単身でもらうための基礎知識としての雑学を記載して行きたい。正直、精神科務めでも勉強していないと知らない・かなり通ぶれる内容になると思う。定期的にアップデートするのでメジャー編まで楽しんでほしい。
少し変わった表現
普通のようにメジャーと表現されるメジャートランキライザーだが聞き慣れない医療従事者も多いかであろう。統合失調症治療薬のことであり。向精神薬ではなく抗精神薬のことである。ちなみにメジャーという表現は単に抗精神薬でない場合もある。それは主剤という意味で使われることもあります。「メジャーでAPZ(エビリファイ)。LP(レボトミン)をムードで使っている」みたいな感じです。
薬の分類は薬効分類ではなく「メジャー、ムード、マイナー」といった使用用途で表現されることも多い印象があります。
一般的科の医療従事者が使うであろう「ベンゾ」なんて表現はしないです。総合失調症のことも「とうしつ」とも表現はしない。BZDはマイナーと表現するし。統合失調症(Schizophrenia)はS(エス)とか「シゾ」と表現します。一般科で「S」は「ステる」とか「死亡」ですね。
抗精神薬の歴史
意外に思われるかもしれないが抗精神薬の歴史は浅い。1950年に世界初の統合失調症治療薬クロルプロマジン(コントミン)が誕生した。抗ヒスタミンの開発の際、偶然できたと考えられている。現在の抗精神薬のほとんどが構造的に抗ヒスタミン派生である。ASP(シクレスト)だけは四環系派生だっか?
では、それまではどう治療していたか?それはショック療法である。
血を抜いてショックを起こさせる。
インスリンでショックを起こさせる。
頭に電流を当てて痙攣を起こさせる。などである。
現在の医療倫理からは考えられないであろう。そもそも中世では魔女に取り憑かれているされた疾患である。ちなみに先に述べた電気ショック療法は患者の身体的精神的不安に考慮した補正型(m−ECT)が現在でも行われている。治療抵抗性の統合失調症や鬱なんかに使われる。
CP換算とは
皆さん好きですよねCP換算。
他にはDAP(ジアゼパム)換算とかイミプラミン換算が有名ですが使い方を間違えば全く使えないです。
一般的にCP換算は抗精神薬をクロルプロマジンで何mg?と理解されている。全く持ってナンセンスである。病院務めの薬剤師の皆様はCP換算を用いて持参薬のエビリファイをリスペリドンに無理くり院内採用薬に代替えさせたことはないだろうか?極めてナンセンスである。この記事を読んだ皆様には是非、今後やめていただきたい。「統合失調症の再燃は治療抵抗性と認知機能低下に直結する」それだけでも覚えておいてほしい。
CP換算とは「精神分裂病患者における治療効果をCP量で表したただの目安」私はこう解釈する。
「精神分裂病患者」と「ただの目安」であることが重要である。
すなわちバイポーラ(双極性感情障害)の治療で用いている場合等は適さない。
適さないというよりそもそもそんな使い方はしない。
「メジャー3種類で治療中でCP換算で800mgで治療してるんだ、ふーん、EPSはでてないかな?頓服と合わしたら1000mg超えるな」ぐらいの感覚で使うものである。
なぜ複数のメジャーで治療するのか
メジャー1剤で寛解できればどんなに理想的か。大抵の場合は主剤+補助薬で治療される。それが先に述べたAPZ+LPのような治療となる。表現は悪いが盥回しにされた患者や足し算のみ行われた場合5種類ぐらいのメジャーが内服されており主剤すら分からない場合も存在する。
メジャーは量によって性格(薬理特性)が変わるものがある。APZやQTP(クエチアピン)何かがその代表である。クエチアピンを内服されているからと言って統合失調症ではい。
メジャーの薬理作用
「D2(ドパミン)受容体遮断薬」とよく周知されていると思う。他にもα、H、M、5ーTH受容体は副作用や薬効の観点から覚えておいた方が良い。
ドパミンだけで通ぶるなら
中脳辺縁系、中脳皮質系、漏斗下垂体系、黒質線条体系について理解しておくと良い。
詳しくは次回解説する。
最後に
いかがだっただろうか?だいぶ通ぶれないか?
最後のに最高の著書を紹介する
ストール神経薬理学
私は初めてこの著書に出会った時はそのセンスの良さに衝撃を覚えました。精神神経薬理学において間違いなく本書は最高峰であると思う。個人的には精神科を生業としている薬剤師には読んでいてほしい一冊である。

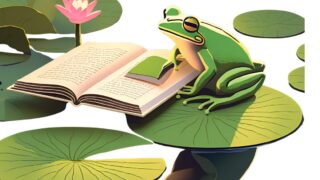



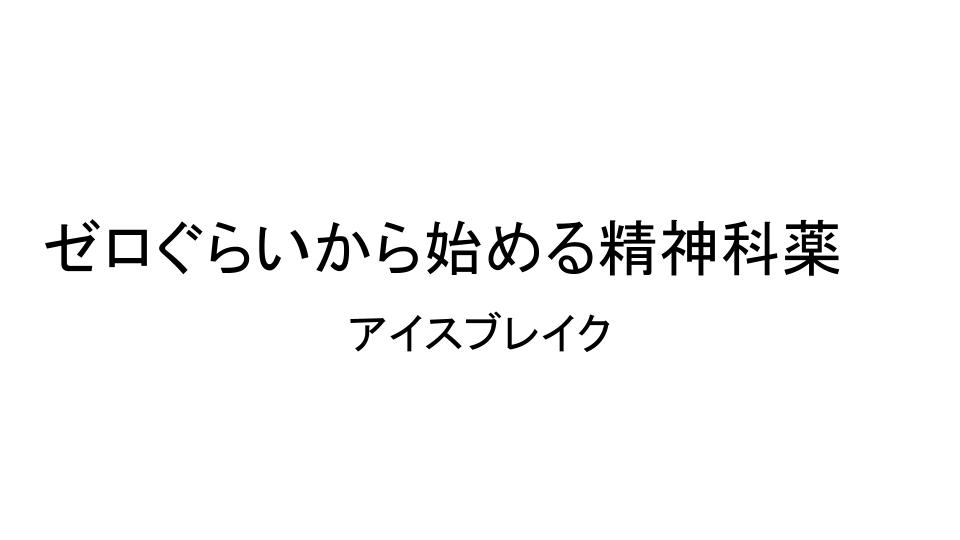


コメント